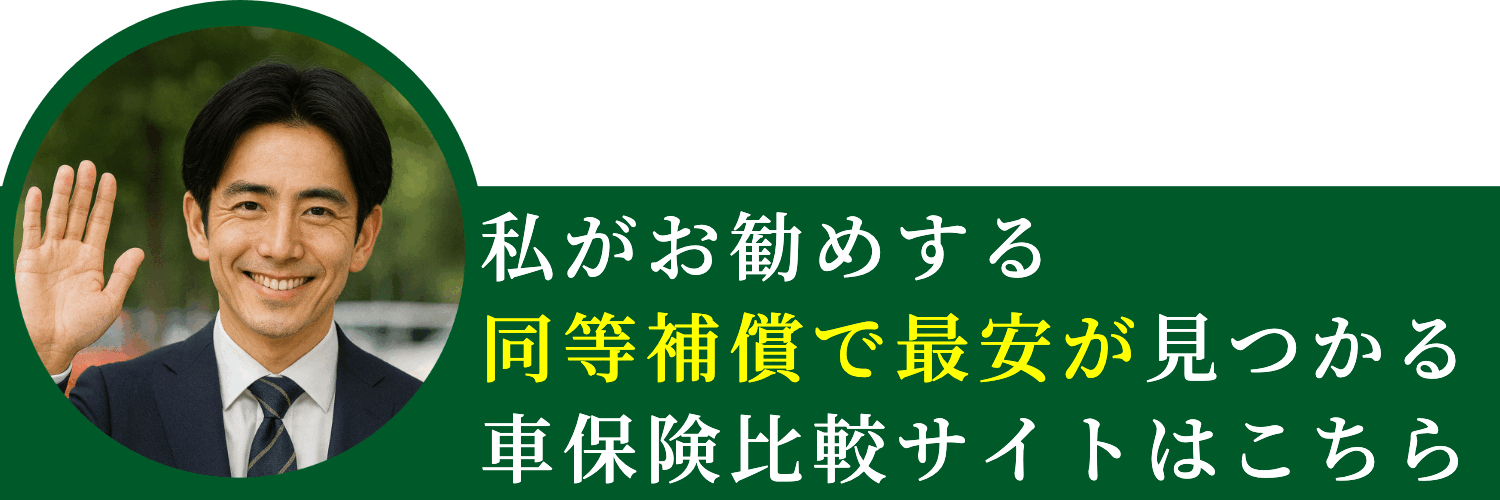自動車保険の更新で「保険料が高くなった」と感じている方も多いでしょう。2025年版では、車両修理費の急騰や交通事故件数の増加、自然災害の多発などが保険料上昇の主な要因と考えられています。
本記事では、自動車保険が高くなった理由や値上げ時期、軽自動車への影響といった最新状況をわかりやすく解説し、保険料を抑えるポイントも紹介します。
自動車保険料がなぜ高騰しているのか、その背景と対応策を押さえて、今後の保険選びに役立てましょう。
目次
自動車保険が高くなった理由とは?
自動車保険料が高くなるのは、保険会社が支払う保険金が増えたためです。ここ数年は車両に搭載される先進安全装置や電子部品が増え、修理費用が従来より大幅に上がっています。部品価格や人件費の上昇も重なり、修理1件あたりの費用負担が増加しました。
また、コロナ禍明けには交通量が回復し、被害が大きい事故が多発しています。事故件数の増加に伴い、人身傷害や対物賠償金の支払いも増加しています。さらに、近年は台風・豪雨といった自然災害が頻発し、多くの車両が被害を受けています。これらの災害による保険金支払いも増加しており、保険料に転嫁されています。
保険は相互扶助の仕組みですから、保険会社が負担する費用が増えれば、それに応じて保険料は高くならざるを得ません。保険会社による一方的な利益確保ではなく、修理費高騰や事故・災害リスク増加に対応するための値上げと考えられます。
以下に、主な要因を詳しく見ていきましょう。
修理費用の高騰
最近の新車には、自動ブレーキやレーンキープアシストなどの先進安全技術(ADAS)が数多く搭載されています。これらの機器を交換・修理するには高度な部品や作業が必要で、修理費用は従来より大幅に高額です。たとえば、前方を監視するカメラ付きのフロントガラスは通常のガラスより数万円高く、バンパーやヘッドライトもセンサーや複雑なLEDユニットを含むため交換費用が大きく上がっています。
また、部品価格の上昇や整備工賃の高騰も続いています。損害保険料率算出機構の調べでは、2024年度に主要各社が純修理代を中心に工賃を3~5%引き上げています。このように1件あたりの修理費用が増加すれば、保険会社が支払う保険金総額も増え、結果的に保険料が上がる要因となります。
交通事故件数の増加
コロナ禍で減少していた交通量は経済回復とともに増加し、それに伴って交通事故の件数も増えています。交通量が増えると高齢者の運転や初心者の運転機会が増え、事故による被害も大きくなりがちです。事故件数が多いほど保険会社の支払う損害賠償金が増加し、保険料に反映されます。
また、一件あたりの賠償額も高額化しています。重傷事故や死亡事故が発生すると、治療費や休業補償、慰謝料なども上乗せされ、保険料上昇の一因となっています。
自然災害の増加
近年は台風や豪雨など自然災害が頻発し、車両保険の請求が増加しています。大雨や台風で車が水没したり、倒木や飛来物で損傷したりすると、被害者は車両保険を利用するケースが多くなります。
例えば2023年の大型台風被害では、数千台規模の車両が浸水被害に遭い、保険会社の支払い負担が一気に膨らみました。自然災害による損害が増えれば、そのコストも保険料に上乗せされるため、保険料高騰の要因になります。
保険料が値上がりした時期と増加幅
2025年1月から保険料が上昇
損保料率算出機構は2024年6月に自動車保険の参考純率を改定し、2025年1月以降の保険料を平均5.7%引き上げることを公表しました。これを受け、多くの保険会社が2025年1月から保険料を改定し、一般的に3~5%の値上げとなっています。
ただし、補償内容や対象車種によってはそれ以上の上昇となるケースもあります。
2025年10月の追加値上げ
さらに、一部の保険会社では2025年10月にも追加の保険料改定が予定されています。報道によれば、この段階で8%前後の大幅な値上げが検討されており、結果的に年内に複数回の値上げ実施が見込まれます。
したがって、2025年10月以降に契約や更新を迎える場合は、保険料がさらに高くなる可能性があります。
契約・更新のタイミングで差が生じる
保険料改定の適用時期は契約開始日または更新日によって決まります。2025年1月1日以降に契約・更新した場合、新しい料率で保険料が計算されますが、それ以前に締結された契約については次回満期まで旧料率が据え置かれる場合があります。
つまり、2024年中に契約や更新を済ませておけば、次の満期までは値上げ前の保険料で継続することができるのです。
軽自動車の保険料はどうなる?
軽自動車を含め、自動車の保険料は車種固有の事故リスクに応じた「型式別料率クラス」で決まります。2025年1月以降、軽自動車のクラスがこれまでの3段階から7段階に細分化されました。クラスが細かくなることで、これまで同じクラスだった車種の間で保険料に差がつきやすくなります。
クラスが引き上げられた車種では保険料が上昇する一方で、リスクが低いと評価された車種ではクラスが据え置きまたは引き下げとなり、保険料負担が軽減される可能性があります。
軽自動車の料率クラス拡大
軽自動車では、2025年1月から適用される新制度で型式別料率クラスが従来の3クラスから7クラスに拡大されました。これは軽自動車の普及・多様化に伴い、車種ごとの事故リスクの違いをより細かく反映するためです。拡大後はクラスの幅が約1.7倍に広がり、車種間のリスク差が保険料に直結しやすくなります。
軽自動車保険料への影響
拡大に伴い、同じ軽自動車でも車種によって保険料への影響が異なります。リスクが高いと判断された車種ではクラスが上がり、保険料が大きく上昇します。例えばダイハツ「ミラ(LA300S)」では、2024年の料率クラスが「3」だった対人賠償が、2025年契約分から「7」に引き上げられました(下表参照)。これにより対人賠償の保険料は約1.2倍に上がる見込みです。
一方で、リスクがそれほど高くない車種ではクラス据え置きまたは引き下げもあり、一律に保険料が上がるわけではありません。
| 補償内容 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 対人賠償 | クラス3 | クラス7 |
| 対物賠償 | 3 | 5 |
| 人身傷害 | 3 | 6 |
| 車両保険 | 2 | 4 |
エコカー割引などの活用
環境性能の高い車両には保険料の優遇制度が用意されています。特に電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)などは「エコカー割引」の対象となり、保険料が若干安くなる場合があります。
また、先進安全装備を搭載する車両向けに割引を行う保険会社もあります。これらの割引制度を活用すれば、軽自動車でも保険料上昇をカバーできる可能性があります。
保険料を抑えるポイント
自動車保険料が上昇する中でも、契約内容や条件を見直すことで保険料を節約する方法があります。
以下では、具体的な節約ポイントを紹介します。
運転者・年齢条件を見直す
運転者限定特約や年齢条件を見直すと、保険料が安くなる場合があります。たとえば、同居家族で運転する人が減った場合は「本人・配偶者限定」などに変更することで割引を受けられます。
また、これまで適用していた「家族限定」や「全年齢補償」を見直して、実際に車を運転する範囲だけに限定することで保険料を抑えられます。一方、子どもが独立して同居ドライバーが減った場合などは、適用年齢条件を上げることで保険料を下げるチャンスです。
車両保険の免責金額を高く設定する
車両保険の自己負担額(免責金額)を高めに設定すると、保険会社の支払い額が減るため保険料が安くなります。
例えば免責金額を0円から5万円に設定すれば、保険料は数千円程度下がることがあります。ただし、万が一事故が発生すると自己負担額が増えるので、どこまで自己負担できるかを考慮して設定しましょう。
割引制度を活用する
多くの保険会社で割引制度が用意されています。
次のような割引が代表的です:
- 無事故割引(等級割引):過去1年間無事故であれば翌年の保険料が安くなる。
- ゴールド免許割引:ゴールド免許所持者が契約者であれば割引される。
- 走行距離割引:年間走行距離が短い場合に適用される。
- エコカー割引:EVやHVなど環境性能の高い車が対象。
- インターネット割引・書面不発行割引:オンライン契約で適用される。
これらの割引を組み合わせることで、保険料を大きく節約できる可能性があります。特にネット申し込みで割引が受けられる会社も多く、同じ補償内容ならダイレクト型保険に乗り換えることで安くなる場合もあります。
保険会社を比較・乗り換える
保険料は保険会社によって差があるため、複数社を比較することも重要です。特にダイレクト(通販)型損保は人件費や事務コストが低い分、一般に代理店型より保険料が安く設定されています。ネットの一括見積サイトを活用し、現在の補償内容と同じ条件で複数社の見積もりを取得しましょう。条件を変えずに保険料だけを比較し、最も安い会社に乗り換えることで節約につながる可能性があります。
まとめ
自動車保険料が高くなった主な理由は、修理費用の高騰や交通事故・自然災害の増加にあります。損保料率算出機構も2025年1月以降の保険料を平均5.7%引き上げており、多くの保険会社で3~5%程度の値上げが実施されました。特に軽自動車は料率クラス改定の影響が大きく、車種によっては保険料が大幅に上がる場合もあるので注意が必要です。
一方で、運転者・年齢条件の見直し、免責金額の設定変更、各種割引制度の活用、保険会社の乗り換えなどによって保険料を抑えることは可能です。
契約更新の際には補償内容と保険料の両方をしっかり確認し、安全運転を心がけながら、最適な条件で保険に加入しましょう。