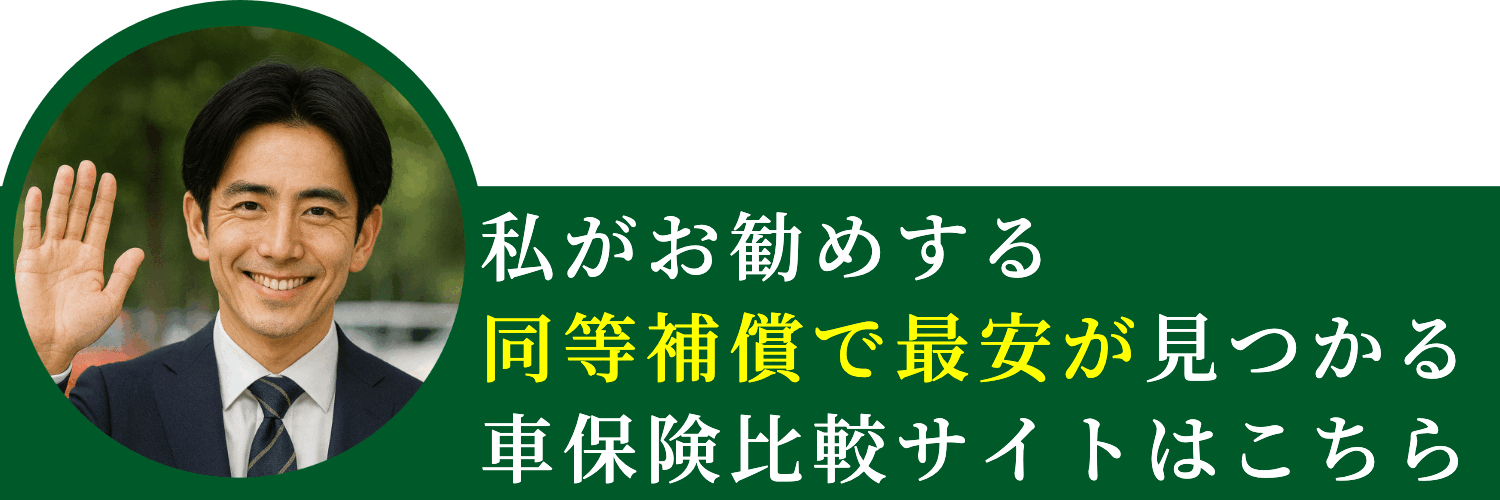もし交通事故の相手が無保険だったとき、自分の補償はどうなるのか不安になる方は多いでしょう。通常、事故では加害者側の任意保険が賠償を担いますが、相手が任意保険に未加入(いわゆる無保険車)であれば、保険の窓口が変わります。
本記事では、相手が無保険の事故で自動車保険がどこまでカバーできるか、被害者側が利用できる補償や制度を詳しく解説します。
事故後の対応方法や弁護士費用特約など、知っておくべきポイントも網羅しますので、安心して催行いただけます。
目次
相手が無保険でも自動車保険で補償される?
交通事故では通常、加害者側の自動車保険(任意保険)の対人賠償・対物賠償で被害者が補償されます。しかし相手が無保険車の場合、任意保険が使えないため補償の仕組みが変わります。
実際には、相手が最低限の強制保険(自賠責保険)に加入していれば人身被害はその枠内で補償されますが、物損(車両修理など)はカバーされません。相手が自賠責にも加入していない完全無保険のケースでは、自分の自動車保険や政府の保障制度などを用いて補償を受ける必要があります。
まず、自分自身の任意保険でカバーできる範囲を確認しましょう。無保険事故でも使える特約や補償(後述の「無保険車傷害特約」「人身傷害保険」「車両保険」など)があれば、被害者の損害を自分の保険で賄える場合があります。特約が付いていない場合や足りない分は、相手との交渉や法的手続き、政府保障制度によって補填する流れになります。
相手が自賠責保険加入・任意保険未加入の場合
相手が無保険でも自賠責には加入しているケース(任意保険のみ未加入)であれば、人身事故の被害は自賠責保険から基本補償を受けられます。自賠責の支払限度額(傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円※いずれも被害者1人あたり)までの範囲で医療費や慰謝料が支払われるため、まずは相手の自賠責保険に請求しましょう。
ただし自賠責は対人のみの補償で、物への補償(対物賠償)は含まれません。つまり、相手が自賠責しか入っていない場合、あなた自身の車両修理費や物損は補償されません。これらは相手に直接請求するか、自分の車両保険(車両損害保険)を使って対応する必要があります。
相手が自賠責・任意とも未加入の場合
相手が自賠責保険にも未加入の「完全無保険車」であれば、通常の保険からは補償が得られません。この場合、被害者自身が加入している保険で補償を受けることになります。具体的には、自身の自動車保険に「無保険車傷害特約」や「人身傷害保険」などが付帯していれば、これらで死亡や後遺障害、治療費などを補填できます。
物損(自分の車両損害)については、車両保険(搭乗者特約なしの一般的な車両保険)を利用します。車両保険に加入していなければ、自費で修理するか、相手と直接交渉するしかありません。いずれにせよ、自分の保険で対応できないときは、政府の保障事業(自賠責法72条に基づく制度)への請求や弁護士介入など、別手段で補償を確保することになります。
自動車保険で補償を受けるための条件
自分の自動車保険で被害をカバーするには、契約内容の確認が必須です。一般に、被害者本人(搭乗者)の傷害には「人身傷害保険」や「死亡・後遺障害保険」があれば本人に支払われます。また、相手が無保険の場合に備える「無保険車傷害特約」が付帯されていれば、遺族や本人への補償が保障されます。
自分の車両損害については「車両保険」が必要です。車両保険があれば、自分の車両損害は契約条件に従って補償されます(無過失事故特約付帯時は自己負担なしで保険対応)。補償に欠ける部分があるときは、相手に不足分を慰謝料などで請求するか、政府制度に頼ることになります。
無保険車とは?自賠責保険と任意保険の違い
「無保険車」とは、法律で加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)にも任意保険にも加入していない車両のことです。実務上は、任意保険だけ未加入の車両がほとんどで、完全無保険(自賠責未加入)は稀です。損保料率算出機構の統計(2024年度)では、任意保険加入率は約88.7%とされており、見積もり約10台に1台が任意保険に未加入となっています。
| 保険の種類 | 補償対象 | 補償上限 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 自賠責保険(強制保険) | 対人賠償のみ | 傷害120万円 死亡3,000万円 後遺4,000万円 |
すべての車両に加入義務あり |
| 任意保険(対人・対物賠償等) | 対人・対物補償(自車および自分の傷害補償も可能) | 対人・対物は上限無制限設定可 | 加入は任意、補償範囲を自由に増減可能 |
自賠責保険は対人賠償だけが対象で補償範囲が限定的です。一方、任意保険は対人・対物だけでなく自分自身のケガや車両損害など幅広い補償を選べ、保険金額も無制限設定ができます。無保険車の場合、相手はこれらの保険を利用できないため、被害者が自身の保険や制度を利用する必要が出てきます。
なお、無保険運転は法律違反であり、例え事故がなくても運転者には罰則が科せられます。自賠責保険未加入で運転すると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に加えて違反点数6点が付与され、免許停止処分になります。厳しい罰則にもかかわらず、無保険車は一定数存在しており、国土交通省と警察が街頭取締りや通報制度で取り締まりを強化しています。
無保険車との事故で被害者が負うリスク
相手が無保険車の事故では、被害者側に通常以上の負担やリスクが生じます。
主なリスクを整理しましょう。
損害賠償金を受け取れない可能性
無保険車との事故では、そもそも加害者側に資力がない場合があります。示談や裁判で損害賠償が認められても、加害者自身に支払能力がなければ実際に賠償金を回収できないことがあります。特に加害者が低所得・無職・未成年などの場合、「今はお金がない」「分割払いならできる」という返答になる可能性があります。この場合、和解しても払い込みが滞ったり、結局被害回復が不十分になるリスクがあります。
自車の修理費や治療費の負担
相手が自賠責のみ加入の場合でも、自賠責は対物(車両)補償がありません。つまり被害者は自車両の修理費用を全額負担しなければならない可能性があります。これを避けるには、自身の車両保険を活用するか、加害者に直接損害賠償請求する必要がありますが、後者は資力次第で実現しないことがあります。
また、被害者側が怪我を負って治療を受ける場合、自賠責保険から120万円までは賄えますが、それ以上の負傷や長期治療が必要になると、自身の人身傷害保険や健康保険などで補填する必要があります。
交渉・手続きが困難になる
通常の事故では双方の保険会社が示談交渉を進めますが、無保険車の場合、加害者側に保険会社の窓口がありません。そのため被害者本人が加害者と直接交渉することになります。交渉が感情的になりやすく、連絡が取れなくなる、相手が示談に応じないといったトラブルが起こりやすいです。
また、後遺障害認定などの複雑な手続きも自身で進めなければならず、手間や時間が増大します。
後遺障害認定手続きの負担
事故で後遺障害が残った場合、通常は相手方の保険会社を通じて後遺障害等級認定の手続きを行えます。しかし相手が無保険車の場合、被害者自身がすべて準備し「被害者請求」として申請する必要があります。専門知識が必要なので、行政書士や弁護士に依頼しないと認定手続きが進まない場合もあり、追加費用・時間がかかる可能性があります。
自分の保険で受けられる補償と利用できる特約
被害者自身が加入している自動車保険にも、無保険車事故で役立つ補償や特約があります。
以下のような保障を確認しましょう。
無保険車傷害保険(特約)
ほとんどの任意保険契約には、無保険車特殊対応の「無保険車傷害特約」が付帯できるようになっています。この特約は、相手が事故の責任者かつ無保険の場合に、自身や同乗者が死亡・後遺障害などを被り、相手から十分な賠償を受けられないときに保険金が支払われます。その補償額は契約通り(多くは無制限)で、自賠責保険でカバーできない分も含めて支払われる仕組みです。万が一の人身事故に備えて、無保険車傷害特約の有無を契約内容で確認し、必要に応じて検討しましょう。
人身傷害保険・搭乗者傷害保険
「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」は、被保険者(契約者)や搭乗者のケガ・死亡に対して保険金が支払われる補償です。相手の任意保険とは無関係に、自分自身や同乗者の治療費や休業補償を受け取れます。無保険の相手との事故であっても、自分の人身傷害保険に基づいて傷害分を補償してもらえるため、治療費の負担を軽減できます。
車両保険・無過失事故特約
自車両の損害については「車両保険」で補償を受けます。無保険車が原因なら自分の車両保険を使えますが、多くの契約では自己負担(免責)が必要です。これを軽減するのが「車両無過失事故対応特約」です。この特約があれば、相手の責任事故でも自分の車両保険に請求し、その事故が自身に全く責任がないと扱われるため、自己負担額なしで修理費が支払われます。特約未付帯の場合は通常の車両保険で支払った後に相手に求償する形になります。
弁護士費用特約
示談交渉や訴訟を弁護士に依頼する場合、「弁護士費用特約」があると相談費用・着手金・報酬を保険会社が負担します。無保険事故では被害者自身が法的手続きを検討するケースが多いため、この特約があれば安心して弁護士へ依頼できます。特約の補償限度額(一般的に300万円程度)の範囲内であれば、交渉や裁判の費用を気にせず進められる点も活用メリットです。
政府保障事業や被害者支援制度を活用する
相手に保険がなく資力もない場合、最後の手段として政府の制度を利用できます。自動車事故に備えた「自賠責保険の保障事業」(政府保障事業)への請求が可能です。国土交通省によれば、2023年度には全国で366件の保障事業の受付があり、その約3割を無保険車事故が占めました。保障事業では自賠責保険と同等の範囲(被害者の対人損害)まで補償されますが、支払額は社会保険等でカバーされる分を差し引く仕組みです。
この制度では被害者本人(または遺族)が申請し、国が加害者に代わって支払う形です。支払限度額は自賠責保険と同じで、対人賠償のみ対象となります。
医療費については健康保険や国民健康保険も活用しましょう。無保険事故で自費で治療を受けた場合でも、健康保険を使えば診療費の負担は大幅に軽減されます。
また、労災保険(勤務中・通勤中の事故)や公的年金制度(障害年金など)が該当すれば適用可能です。これらを組み合わせることで、一時的な資金負担を小さくできます。
示談・賠償請求の進め方:無保険事故の場合
無保険車との事故では、被害者側が主体的に示談交渉や賠償請求を進める必要があります。まず事故直後には、警察や保険会社に連絡し、診断書や修理見積もりなど必要書類を整えましょう。
以下に、一般的な進め方の一例を挙げます。
加害者との示談交渉のポイント
加害者が任意保険業者ではなく個人の場合、被害者は相手方と自ら交渉します。この際、事故の状況証拠(写真、ドライブレコーダー映像、実況見分調書など)をしっかりと残し、過失割合や損害額を明確に主張しましょう。示談案を提案するときは、損害賠償内訳(治療費、休業損害、車両修理費、慰謝料など)を具体的に示し、相手に理解しやすい内容にするのがポイントです。万一相手が一括支払いに応じない場合でも、分割払いや将来の差押えを匂わせるなど圧力をかけ、誠意ある対応を求めます。
示談合意できない場合の内容証明
示談協議が難航したり相手が連絡を絶った場合は、内容証明郵便で正式に賠償請求を行うことが有効です。内容証明郵便とは、いつ誰がどんな文書を送付したかを郵便局が証明する手段です。被害者請求の意思表示と請求金額、期限などを明確に記載して相手に送り、法的な証拠とします。相手に対し「遅延損害金請求の意思」「裁判準備中の意思」を示せるため、示談交渉がスムーズになる場合があります。
訴訟と強制執行による回収
示談も内容証明も効かない場合、裁判(民事訴訟)で損害賠償を請求します。訴状を裁判所に提出し、判決で賠償命令を得ましょう。勝訴すると判決確定後、相手の給料・預貯金など財産に対して「強制執行」が可能です。強制執行により、差し押さえた財産を換価して損害額を回収できます。ただし手続きには数カ月~数年以上かかる場合があるため、専門家(弁護士)に相談しつつ適切な対応を進めることが大切です。
まとめ
相手が無保険車の場合、事故後の補償確保には通常以上の工夫が必要です。事故直後の手続きでは、自賠責保険の請求や自身の保険会社への連絡を忘れずに行いましょう。被害者自身が加入している自動車保険の補償内容(人身傷害保険や無保険車特約、車両保険など)を確認し、使える保障は可能な限り活用することが重要です。
それでも補償が足りない場合は、政府の保障事業や各種公的保険制度も検討しましょう。示談交渉は記録を取りながら慎重に行い、交渉が難航する場合は内容証明や訴訟の利用も辞さない姿勢が必要です。
無保険事故は被害者にとって負担が大きいため、早めに保険会社や専門家に相談し、余裕を持った対処を心がけましょう。