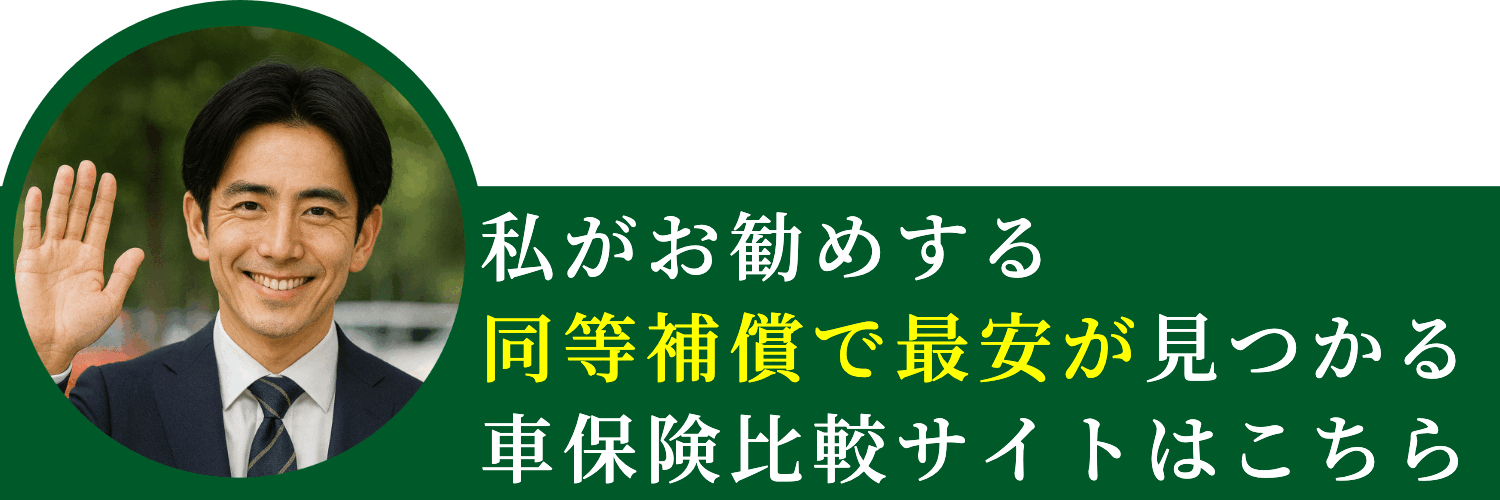お勤め先の会社や団体を通じて自動車保険に加入する「グループ割引」を活用すると、保険料が大きく節約できる可能性があります。割引率は最大30%にも達し、多人数で加入するほど割引メリットも高まります。近年は保険料の水準が上昇傾向にあるため、節約手段としての団体割引が注目されています。特に2025年には基準純率改定で保険料が上昇する見通しのため、団体割引による節約は家計の強い味方となるでしょう。
本記事ではグループ割引の仕組みやメリット、加入方法などをわかりやすく解説します。
目次
自動車保険におけるグループ割引とは?
グループ割引は「団体扱い契約」とも呼ばれ、企業や団体に所属する従業員・役職員を対象に提供される割引制度です。加入者が多くなるほど保険会社は保険料の管理コストを抑えられるため、大口割引を適用して保険料を低く設定します。例えば、会社の福利厚生制度として団体扱いの自動車保険が用意されている場合、個人契約と比べて割引率が高くなることがあります。
団体扱い契約では、契約者は従業員本人ですが、支払いには給与天引きなどが利用できます。保険料を事前に払う必要がなく、契約手続き後は給与から自動的に支払われるため、手続きが簡単で支払い漏れの心配も少ない点も特徴です。
加入できる対象者は、主に企業や団体に勤務する従業員・役職員、その配偶者や扶養される家族などです。団体扱いの自動車保険では、契約者である従業員本人に加えて、契約者の配偶者や同居の親族を記名被保険者とすることで、家族の車も割安な保険料で加入できるケースがあります。
団体扱契約と団体契約の違い
団体割引には「団体扱契約」と「団体契約」の2種類があります。
どちらも多くの加入者をまとめて契約する点は共通しますが、契約の主体や割引率に違いがあります。
| 項目 | 団体扱契約 | 団体契約 |
|---|---|---|
| 契約者 | 従業員・役職員(個人) | 企業や団体 |
| 保険証券 | 契約ごとに加入者個人に発行 | 企業に1通のみ発行(個人証は企業経由で配付) |
| 割引率の目安 | 一般に3~30%程度 | 一般に5~50%程度 |
| 保険料支払 | 給与天引きなど個人負担を軽減 | 同左(企業が集金) |
上記のように、団体扱契約は従業員個人が契約者となって保険証券も個人に発行されます。
一方、団体契約では企業や団体が契約者となり、保険証券は団体に1通だけ発行されます。割引率は一般的に団体契約のほうがさらに高い傾向にありますが、その分、団体契約では加入の条件が厳しくなるケースが多い点が特徴です。
グループ割引の割引率と節約効果
団体割引の割引率は、団体の規模や過去の事故実績(損害率)によって決まります。団体に加入する人数が多く、事故率が低いほど、より高い割引率が適用されやすくなります。一般的には団体扱契約で3~30%程度、団体契約では5~50%程度が目安です。実際に大企業や公的機関などでは、30%前後の割引率が設定されることもあります。
最大で約30%もの割引が受けられるグループ割引は、保険料が高額な車種や等級が低い契約ほど、節約効果が大きくなる傾向があります。たとえば、自動車保険料が年間10万円の場合、単純計算で30%割引なら年間3万円の節約になります。逆に5%程度の割引率では節約額が少なくなるため、契約前に割引率を確認しておくと安心です。
なお、割引率は年度ごとに見直されます。実際2024年10月には高速道路運営会社グループの団体割引率が30%から25%に変更されるなど、損害率の変動によって割引率が上下する例があります。2025年以降も引き続き割引率の改定が予想されているため、契約更新の際には最新の割引率をチェックしましょう。
グループ割引のメリットと注意点
メリット
団体割引の主なメリットは保険料が割安になることです。複数の契約をまとめることで大口割引が効き、個人契約よりも保険料負担を軽減できます。また、保険料は給与天引きなどで支払えるため、事前に保険料を用意する必要がない点も大きなメリットです。そのため、契約完了後は支払い漏れの心配なくいつでも補償を受けられます。さらに、契約者本人と別名義の家族車も割引対象にできるケースがあるため、家族全体の保険料も安く抑えやすくなります。
- 保険料が通常契約より大幅に割安になる
- 給与天引き等で保険料の支払いが簡便(事前払なし)
- 契約者と異なる名義の家族車でも割引対象にできる
注意点
団体割引にはいくつか確認すべき点もあります。割引率が高くても、団体割引は代理店型保険に限られるため、通販型(ネット型)自動車保険と比較すると割高になる可能性があります。割引率次第では、通信販売型の保険のほうが安くなるケースもあるため、加入前に複数社で保険料を比較すると安心です。
また、団体扱い契約はあくまで企業・団体に所属している間の割引です。転職や退職によってその団体の対象外になると団体割引は適用対象外となりますので、退職時の手続きや転職先の団体契約の有無は事前に確認しておきましょう。
- 割引率が低いときは他の保険と比較検討する
- 団体契約は個人契約より保険料が高くなる可能性もある
- 退職や転職で団体割引が使えなくなるリスクがある
グループ割引が利用できる団体と申し込み方法
対象となる団体・組織の例
団体割引を利用できるのは、一般的に従業員規模の大きい企業や公的機関、業界団体などです。例えば、大手メーカーや官公庁の組合、鉄道会社・電力会社・大型物流企業などでは従業員向け団体扱い保険が用意されていることがあります。
また、医師会や弁護士会といった職域団体、協同組合、業界の福利厚生協会などでも独自に団体保険を設定している場合があります。自分の勤務先や所属する組織で団体扱いの自動車保険が適用できないか、一度確認してみることをおすすめします。
加入方法と手続き
団体割引を利用するには、まず勤務先や所属団体に団体扱い自動車保険の制度があるかを確認します。加入対象者であれば、所属先の総務部門や保険担当部署、もしくは団体扱い保険を扱う代理店に問い合わせましょう。多くの場合、専用の申込用紙やウェブフォームが用意されており、車両情報や契約者情報を提出するだけで手続きできます。支払いは給与天引きが一般的ですが、一括払いも選べることがあります。万が一卒業・退職などで団体割引が使えなくなるときは、代理店に相談して個人契約への切り替え手続きを行うことが必要です。
まとめ
団体扱いの自動車保険(グループ割引)を利用すれば、割引率に応じて保険料を数千円~数万円単位で安く抑えられる可能性があります。特に大規模組織や公的機関に勤めている場合は、高い割引率が設定されやすく節約効果も大きいでしょう。
一方、割引率や保険内容は団体ごとに異なるため、契約前には必ず内容を確認し、必要に応じて他の保険料と比較検討してください。
団体割引はあくまで補助的な制度ですが、条件が合えば大きな節約につながるため、勤務先や所属団体の制度を活用して賢く保険料を見直しましょう。