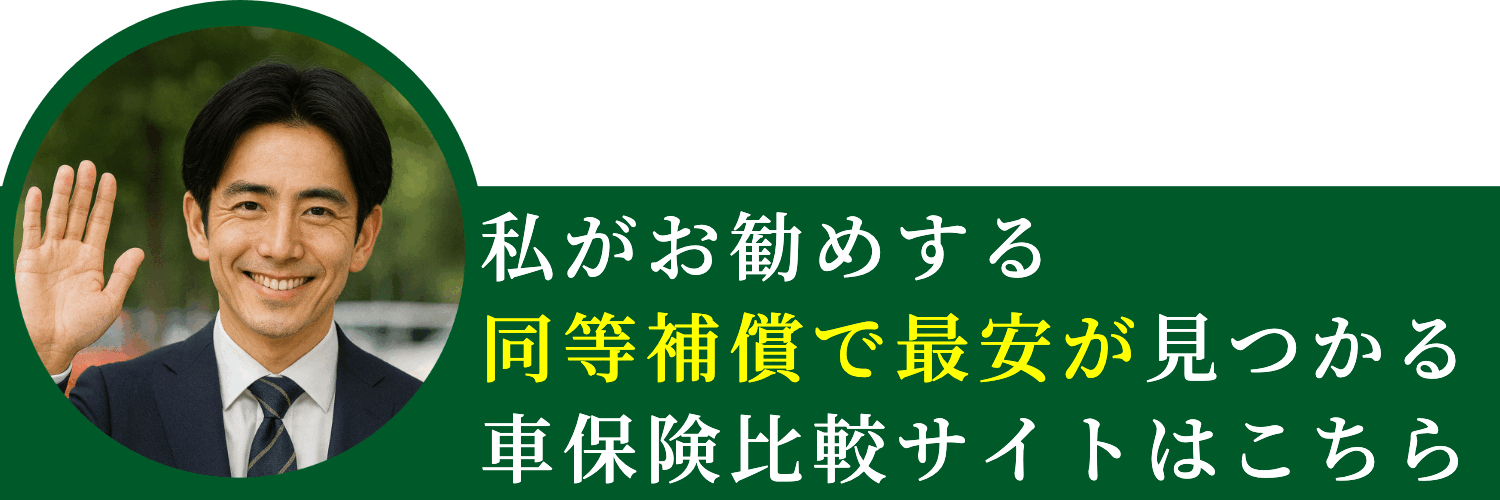近年、自動車保険料が年々上昇し、多くのドライバーが契約更新時に「保険料が高くなった」と感じています。
本記事では、保険料が高騰する背景として、交通量の増加や自然災害の多発、修理費用や部品代の高騰といった要因を解説します。
また、保険料の算出方法や料率クラス・等級制度といった仕組み、さらに保険料を抑える具体的な方法についても紹介します。
自動車保険は年々高くなる?その原因と背景
自動車保険料の増加傾向には複数の要因が関係しています。主に考えられるのは、交通事故件数の増加や自然災害による被害急増、さらに車両修理費用の高騰です。
これら要因が組み合わさることで、保険会社の支出が増え、その結果として保険料に反映されていきます。
交通量増加と事故件数の増加
コロナ禍が収束に向かい交通量が回復すると、事故件数も増加傾向にあります。
交通量が増えるほど自動車同士や歩行者との接触機会が増え、事故の発生確率が高まります。
事故が増加すれば保険金支払いが増えるため、車両保険料を含む保険料総額への影響は大きいです。
こうした傾向は事故リスクの上昇として保険料に上乗せされ、年々保険料を押し上げる一因になります。
自然災害の影響
近年、日本では台風や集中豪雨、地震など大規模な自然災害が頻発しています。
これら自然災害により多くの車両が水没や衝突被害を受け、車両保険の請求件数や一件当たりの支払い額が増加しています。
例えば豪雨災害で車両が流出・水没すれば修理不能と判断され高額賠償になるケースもあるため、保険会社の負担が増大します。
このように災害リスクの高まりは保険会社の予算に影響し、結果的に保険料値上げが必要になります。
先進安全装備の普及と修理費用
近年、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全装備(ADAS)が一般車にも普及しています。
これら装備には高価なセンサーやカメラが搭載されており、事故時にはバンパーやフロントガラスだけでなく、レーダー・センサー・カメラ本体の交換が必要になることがあります。
こうした高性能部品の交換修理は従来に比べて費用が非常に高く、加えて人件費や部品価格の世界的なインフレも重なって修理コストは年々上昇しています。
保険会社はこれらのコスト増加を保険料に反映せざるを得ず、結果として年を追うごとに保険料が高くなる傾向が生まれています。
自動車保険料 決定のポイント
自動車保険料は、車両特性やドライバーの属性、過去の事故歴など複数のリスク要因を組み合わせて決定します。
日本では損害保険料率算出機構が集計した統計データを基に保険料率が算定され、各保険会社はその基礎となる料率を参考に保険料を設定します。
次に、具体的な保険料決定の主なポイントを説明します。
損害保険料率算出機構と保険料の算出
損害保険料率算出機構は、保険会社が保有する膨大な事故データを収集・分析し、保険料の基礎となる「参考純率」や「基準料率」を算出します。
この機構は基礎数値として毎年自動車保険の参考純率を公表し、必要に応じて料率改定案を金融庁に届け出ます。
各保険会社はここで算出された基礎数値を見て、自社の補償内容や割引を反映させて最終保険料を決定します。
つまり、事故件数や支払い額などの統計に変化があれば、算出機構が保険料率を見直し、その結果として私たちの保険料にも影響が出ます。
型式別料率クラスの仕組み
型式別料率クラス制度は、車種(型式)ごとの事故実績に応じて保険料率に差をつける仕組みです。
事故が多い車種は高い料率クラスに、事故が少ない車種は低いクラスに分類され、クラスが上がるほど保険料は割高になります。
料率クラスは毎年見直されており、2025年からは軽自動車のクラスが従来の3クラスから7クラスへ拡大されます。
例えば、ダイハツ ミラ(型式LA300S)では2024年にすべての補償タイプでクラス3でしたが、2025年以降は対人賠償でクラス7、対物賠償でクラス5、人身傷害でクラス6、車両保険でクラス4に変わります。
| 補償内容 | 2024年 (ミラ LA300S) | 2025年 (改定後) |
|---|---|---|
| 対人賠償責任保険 | クラス3 | クラス7 |
| 対物賠償責任保険 | クラス3 | クラス5 |
| 人身傷害保険 | クラス3 | クラス6 |
| 車両保険 | クラス2 | クラス4 |
このように同じ車種でも補償内容によってクラスが異なり、改定後は高いクラスになると保険料負担が増加する可能性があります。
年齢条件・等級制度と割引
ドライバーの年齢条件や保険契約の等級(ノンフリート等級)も保険料に大きく影響します。
若いドライバーほど事故リスクが高くなるため、年齢条件区分を「全年齢対象」にしていると保険料は高めです。一方で同棲や結婚で最も若い運転者が年上になると「21歳以上限定」などに変更でき、保険料を抑えられる可能性があります。
また、等級制度では無事故なら契約を更新するごとに等級が1つ上がり割引率が増えますが、事故を起こすと等級が下がり割引が減ります(※事故有係数が連続適用)。
無事故なら長期間で大きな割引を得られますが、事故歴があると保険料が割高になる仕組みなので、たとえ保険を使わない修理でも軽い事故扱いで等級が下がることに注意が必要です。
2025年の保険料改定と今後の動向
2025年1月から、多くの大手損保会社で自動車保険料率の改定が実施され、保険料引き上げが見込まれています。
具体的には、保険会社や契約内容によって異なりますが、おおよそ3.5%~5%程度の値上げが予定されています。
この背景には、前章で挙げた事故増加や自然災害の増加に加え、世界的な物価高騰により部品代や修理費が高騰していることがあります。今後も修理費や人件費の上昇は続く見通しで、保険料への影響が懸念されています。
2025年1月の値上げ予定
既に発表されている通り、大手4社をはじめとする損保会社では2025年1月以降の契約更新から保険料を改定し、値上げする方針です。
具体的な値上げ率は契約の条件や車種によりますが、多くの顧客で3~5%の増加が報告されています。
これに対し、保険加入者は高さを実感するでしょう。対策としては、2024年中に契約更新や乗り換えを行い、旧料率の適用を受ける方法が取られています。
軽自動車の型式別料率クラス拡大
前述の通り、2025年1月から軽自動車の型式別料率クラスが拡大されます(従来は3クラス→新基準で7クラス)。
これにより、もともと安全性能が高いとされた軽自動車も、安全装備の違いや事故歴などに応じて高めのクラスに分類される可能性があります。
たとえば従来クラス3だった軽自動車が、改定後にはクラス6や7に上がることもあり得ます。
結果として、これまで軽自動車であまり保険料が変わらなかった契約者でも、突然保険料が跳ね上がる可能性がありますので注意が必要です。
物価高騰と修理費の継続的影響
車両関連費用の高騰は2025年以降も続く見込みです。
世界的な部品供給の逼迫や人手不足に伴い、修理部品の価格や工賃は上昇傾向が続いています。
自動車に使われる半導体不足もあり、生産コストが上がった車両価格が事故時の補償額に反映されます。
これらの影響で、保険会社が過去のデータを使って料率を設定する際の基準となるコストが高止まりし、長期的に高い保険料水準が続く可能性が高い状況です。
事故と保険料の関係
自動車保険では事故歴が保険料に大きく影響します。
事故を起こすと、契約時のノンフリート等級がダウンし、次回以降の保険料割引率が下がります。
また「事故有係数」が適用され、事故後数年間にわたり割増率が加算されるため、保険料はさらに高くなります。
「等級ダウン」と「事故有係数」の仕組みを理解しておくことが重要です。
等級ダウンと事故有係数
日本の自動車保険では、無事故の年数に応じて1~20等級の割引等級(ノンフリート等級)が設定されます。
事故を起こして保険を利用すると、等級が3等級分(主に対物事故時)または1等級分(小さなキズのみの修理など)下がります。
加えて事故歴の有無に応じて一定期間割増(事故有係数)が適用されるため、数年間は保険料が高いままとなります。
例えば10等級で電柱に衝突事故を起こすと、等級は7等級に下がり、さらに3年間は事故有係数が付くため保険料は大幅に上昇します。
無事故連続による割引メリット
逆に、無事故であれば等級が1つずつ上昇し、毎年の割引率が増えていきます。
長年事故ゼロで更新を続ければ、20等級という最高割引率に到達し、同じ補償内容でも保険料が最も安くなります。
無事故連続でコツコツ積み重ねた等級割引は保険料抑制に大きな効果があります。
ただし、先にも述べた通り、無事故だからと言って必ずしも毎年保険料が下がるわけではありません。契約条件を変更していない場合であっても、料率基準の見直しや車両型式の変更など外的要因で保険料が上がることもあります。
自動車保険料を抑える方法
保険料上昇に悩む契約者は、以下のような対策で保険料の節約を検討できます。
契約内容の見直しや割引制度の活用、他社比較を行い、少しでも保険料負担を減らしましょう。
補償内容と契約条件の見直し
補償内容や契約条件を見直すことで保険料を抑えられます。
- 車両保険の範囲を限定する(車両保険を外す・フルカバーからエコノミータイプに変更)
- 免責金額を引き上げる(自己負担額を増やすほど保険料は下がる)
- 運転者限定や年齢条件を絞る(同居家族で最も若い運転者の年齢を上げ、運転者の範囲を限定する)
- 不要な特約を外す(人身傷害の範囲を狭くする、ロードサービス割増を省くなど)
これらは一度契約してからも変更できます。例えば子供が独立して同居者が高齢になった場合は年齢条件を見直し、若い運転者がいなくなった場合は運転者限定を「本人・配偶者限定」にすることで保険料を下げるチャンスがあります。
割引制度の活用
各種割引制度を積極的に活用する方法も効果的です。
- Internet割引やダイレクト(ネット申し込み)割引:ネット通販型保険の契約で割引が適用されることが多い
- 長期契約割引:2年契約や3年契約にすると割引が受けられる場合がある
- ゴールド免許割引:無違反の優良ドライバーは料金の割引対象になる
これらを組み合わせることで保険料が数千円から数万円単位で安くなる可能性があります。たとえばネット申込で上記の複数割引を併用すれば、無保険状態でも大幅な節約につながる場合があります。
保険会社の比較・乗り換え
同じ補償内容であっても、保険会社によって保険料には違いがあります。
一般的に通販型(ネット系)保険は、代理店手数料や人件費がかからないため代理店型より保険料が安い傾向にあります。
複数社の見積もりを比較し、より安いプランへ乗り換えることで保険料を抑えられることがあります。
一括見積サイトなどを活用すると手間をかけずに料金比較ができるので、数社から見積もりを取り寄せて検討するのがおすすめです。定期的に他社との保険料を比べ、必要に応じて乗り換えを検討しましょう。
まとめ
以上、自動車保険料が年々高くなる背景と仕組み、そして保険料を抑えるポイントを解説しました。近年の事故増加や自然災害、車両修理費の高騰などが保険料値上げの主な要因であり、2025年には損害率の見直しにより各社で値上げが予定されています。
保険料を抑えるには、補償内容や契約条件の見直し・各種割引制度の活用・他社比較による乗り換えなど、できる対策を総合的に検討することが重要です。
信頼できる保険会社を選ぶとともに、自身の運転状況・車両状況に応じて保険プランを適宜見直し、無駄を省いた賢い保険選びを心がけましょう。